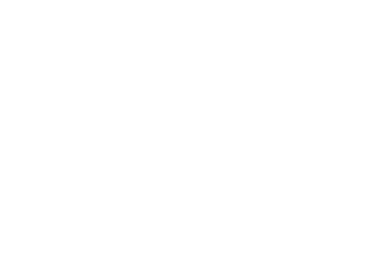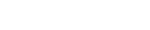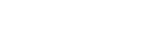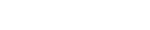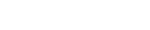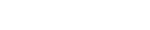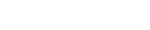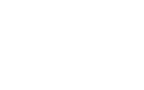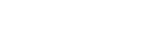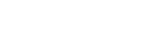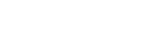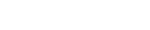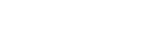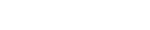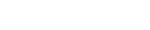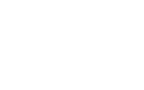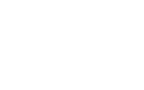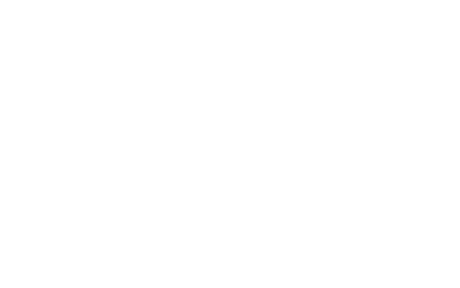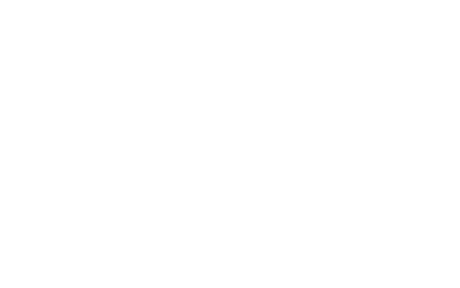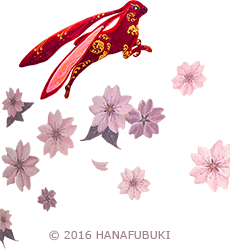宿を楽しむ旅、5000坪の森の中に佇む白翁棟

伊豆高原は富士箱根伊豆国立公園に指定された、天城の山々、大室山、城ヶ崎海岸という豊かな自然に恵まれたリゾート地。観光やアウトドアを楽しむのも良いところであるけれど、その豊かな自然に耳を傾ける旅はどうだろう。
あえて何もしない贅沢な時間を過ごす…>続きを読む
2025.05.21
花吹雪の桜おこわでプライベート観桜会

伊豆高原の桜並木は染井吉野が満開だと聞いて、今回のショートトリップは友人夫妻とプライベート観桜会と洒落込んでみることにした。桜のトンネルを抜けると伊豆高原の別荘地が広がる。
お花見というと、桜の木の下で宴会のイメージがあるが、そもそもお花…>続きを読む
2025.04.07
静岡県産鰻の白焼き、紅姫あまご燻製炊き込み御飯

倶楽部ハウスで夕食の席に案内され、席に着くとその日の「長七お献立」が置かれている。これからいただく料理が記されているメニューを確認するのも楽しみのひとつ。大切なおもてなしのペーパーアイテムだ。先付から始まる献立を目で追うだけで今日のお酒が美味くなる…>続きを読む
2024.06.03
花吹雪の新しい宿泊棟「万葉の棟」特集

5月にオープンした別館・万葉の棟は、倶楽部ハウスと道を挟んだ向かい側の森の中に佇む宿泊棟。低木から高木まで豊かに茂る小さな森は、小鳥の囀りと、木漏れ日の温もりが心地よい。木立を抜けていく径には、染井吉野、山桜、紅葉など四季を楽しめそうな木々。柔らか…>続きを読む
2024.06.03
金目鯛桜葉〆、八重桜と天城山葵のソルベ

小彼岸桜の満開を迎える頃には、貝や春野菜など旬の恵みがふんだんにあしらわれて夕餉の献立も随分春を装ってくる。
八寸:蕗と蕗の薹の白和え、地物黒鯛の昆布〆小袖寿司、天城産山葵の三杯酢、静岡県産ばい貝の旨煮、蛍烏賊とたらの芽の芥子酢味噌掛け
大人の…>続きを読む
2024.04.08
伊豆高原の春だより「染井吉野と小彼岸桜の競演」

伊豆高原の桜前線は、3月に入って予想外の寒さに停滞していた。
晦日になってまるで手のひらを返した様に汗ばむほどの真夏日となり、花吹雪では日本の色棟前の染井吉野と森の園の小彼岸桜が一気に満開となった。こんな日に滞在できるとはなんとも幸運である。
…>続きを読む
2024.04.04
森のカフェ、森の宿に吹く緑の風

鶯は歌が随分上手くなった。寒桜の頃は初鳴きで、たどたどしい調子で鳴いていた。春もたけなわとなり、ずいぶん練習を重ねたのだろう。鶯の谷渡りと喩えられるように伊豆高原の森に澄んだ声だけが響いている。
森は若葉が芽吹き、こんもり…>続きを読む
2023.05.01
春蘭、桜葉、うど、こごみ、春の和ハーブをいただく

伊豆高原は春爛漫。河津桜が葉桜になって、大寒桜、おかめ桜、染井吉野と桜の開花リレーが続いていく。富士箱根伊豆国立公園の緑も芽吹きが始まった。日本に自生する有用植物、和ハーブは香りの効能、食する効能があり、季節の移り変わりに添って芽を出し、花開き、実…>続きを読む
2023.03.13
「メジロと桜」伊豆高原の春だより

1月の中旬には河津桜の一番花が咲く伊豆高原。どこより早い桜の開花は「春は伊豆から」というキャッチフレーズが似合う。河津桜の開花は実のところ、河津より伊豆高原の方が早い。大寒波のニュースの中でささやかな春の知らせをお届けしたい。
土脉潤起(つち…>続きを読む
2023.02.20
伊豆高原の黒文字精油とヤブニッケイ精油の魅力

日本における香りの文化は「祈り」とともに歴史を刻み、広がっていったとも言われている。香を焚くことから始まり、現代ではエッセンシャルオイルと呼ばれる植物の香り成分「精油」が生活文化に取り入れられている。
近年、注目されている「和精油」とは
天…>続きを読む
2022.05.30
最近の記事
月別アーカイブ
- 2025 / 7
- 2025 / 6
- 2025 / 5
- 2025 / 4
- 2025 / 2
- 2025 / 1
- 2024 / 12
- 2024 / 10
- 2024 / 9
- 2024 / 7
- 2024 / 6
- 2024 / 4
- 2024 / 2
- 2024 / 1
- 2023 / 12
- 2023 / 11
- 2023 / 10
- 2023 / 8
- 2023 / 7
- 2023 / 5
- 2023 / 3
- 2023 / 2
- 2022 / 12
- 2022 / 11
- 2022 / 10
- 2022 / 9
- 2022 / 6
- 2022 / 5
- 2022 / 4
- 2022 / 3
- 2022 / 2
- 2022 / 1
- 2021 / 11
- 2021 / 7
- 2021 / 6
- 2021 / 5
- 2021 / 3
- 2021 / 2
- 2020 / 11
- 2020 / 10
- 2020 / 7
- 2020 / 6
- 2020 / 4
- 2020 / 3
- 2020 / 1
- 2019 / 11
- 2019 / 10
- 2019 / 9
- 2019 / 8
- 2019 / 7
- 2019 / 6
- 2019 / 5
- 2019 / 4
- 2019 / 3
- 2019 / 2
- 2017 / 2
- 2016 / 10